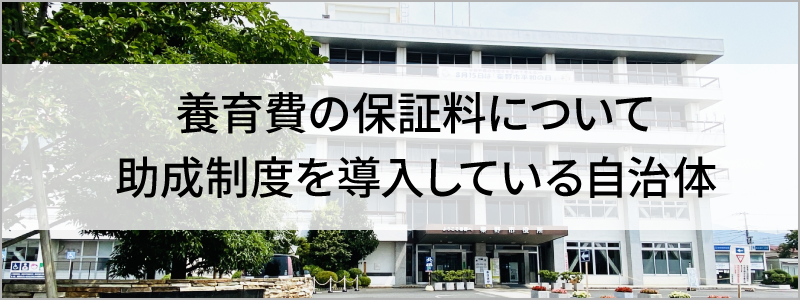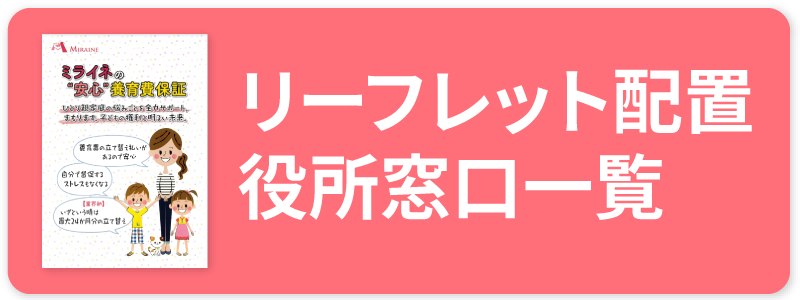ひとり親の年金支払い免除・納付猶予制度とは?
ひとり親の平均年収はご存知ですか?
父子家庭は420万円、母子家庭は243万円です。さらに、母子家庭に関しては、就業率約80%となっており、ひとりで子育てをしながら就業することの難しさを物語っています。
いろいろな支払いがあるなか、月額16,590円(令和4年4月〜令和5年3月までの金額)の年金の支払いは大きな負担となるでしょう。
そこで今回は、ひとり親世帯も活用できる年金支払い免除・納付猶予について解説します。
国民年金免除・納付猶予制度とは
国民年金免除制度とは、ひとり親世帯に限らず、収入の減少や失業など、保険料を納付することが難しい場合に利用できる制度です。ひとり親世帯に限らず、免除申請をすることが可能です。
納付猶予と免除について、詳しくみていきましょう。
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
保険料免除制度
所得が少なく、前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料免除・納付猶予の基準
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)× 35万円 + 32万円 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 - 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数 + 1)× 35万円 + 32万円
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。また、地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、該当の年金事務所へお問合せください。
手続きをするメリット
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。) - 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
受給する年金額を増やすには
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める必要があります。
保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱われます。
保険料を未納のままにしてくと
- 障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(※)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
- 老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
上記のようなデメリットがあります。
保険料の支払いが難しい場合は、免除・納付猶予申請をすることをおすすめいたします。
養育費保証のミライネ
『養育費保証のミライネ』では、養育費を継続的に受け取るためのプランをご用意しております。継続的に養育費を受け取ることは、大切なお子様のためになります。お子様の未来のため、そしてひとり親の方々だけに負担がないように、養育費は必ず受け取りましょう。
養育費に関して、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。