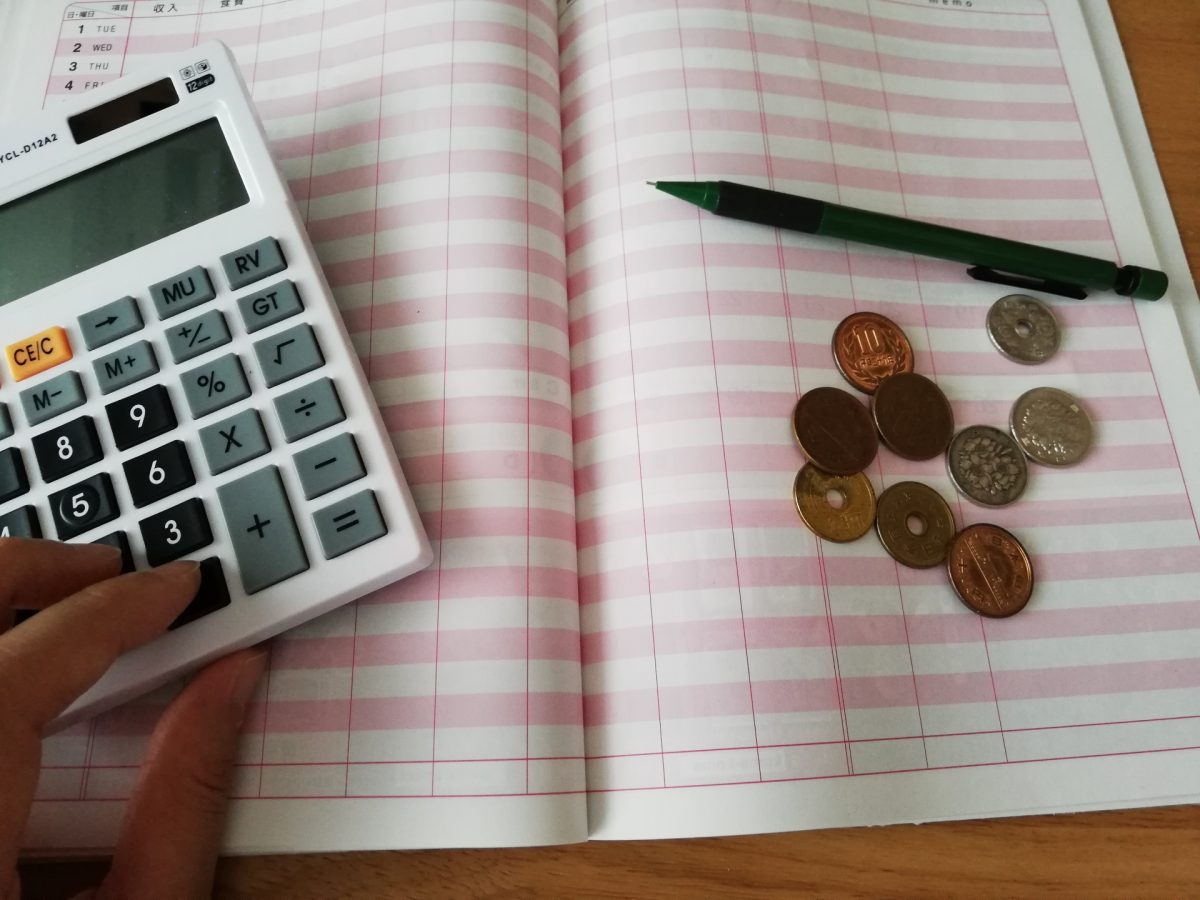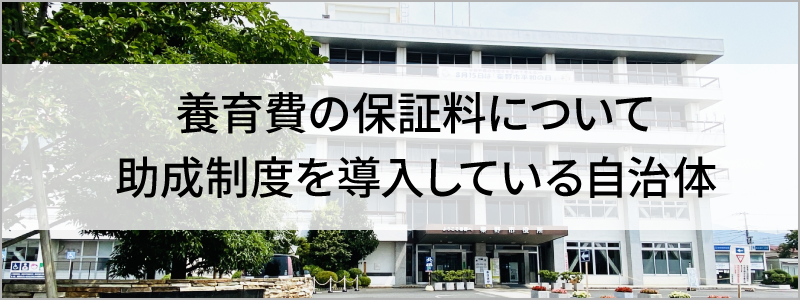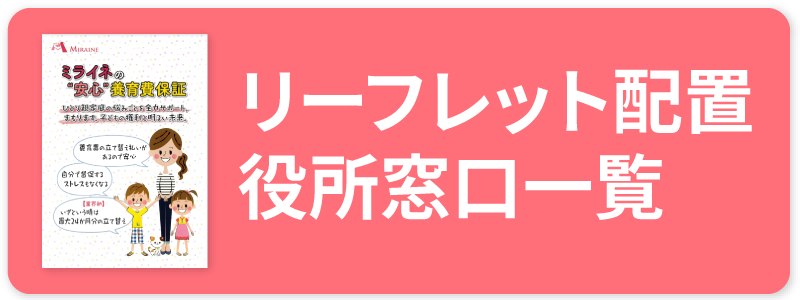ひとり親世帯が生活保護を受ける4つの条件〜後編〜
- 公開日
- カテゴリー
- 養育費
前編では、生活保護の基本的な部分をご紹介しました。
今回の後編では、ひとり親世帯における生活保護受給について、手当との兼ね合いや注意点・デメリットなど、さらに詳しくご紹介します。
母子加算とは
生活保護の申請前に受けた手当等は、収入という扱いになりますが、児童扶養手当などの手当と生活保護を同時に受けることも可能です。
児童扶養手当などの公的な手当を受給している場合、最低生活費から公的手当分を差し引いた残りが、生活保護の受給額となります。
また、ひとり親世帯の場合は、母子(父子)加算という制度があります。
では、母子加算とはどのようなものかというと、“一方の配偶者が欠ける状況にある者が児童を養育しなければならない”といった場合に加算されるものです。母子加算という名称ではありますが、父子家庭であっても加算対象となります。つまり、生活保護を受けている世帯が、ひとり親世帯の場合に支給されるということになります。
母子加算は、児童扶養手当と連動しているため、
児童扶養手当が受給できる=母子加算が行われる
児童扶養手当が受給できない=母子加算が行われない
ということになります。
ただし、児童扶養手当と母子加算はあくまで別制度であり、児童扶養手当が受給できなくても母子加算が行われる、またその逆もあります。
母子加算の加算額
母子加算の加算額については、住んでいる地域の“級地”と子供の人数によって異なります。級地については、厚生労働省HPで確認することができます。
基本額は以下となっています。
- 1級地
児童が1人の場合 18,000円
児童が2人の場合 1人分18,000円+4,800円
児童が3人以上1人増えるごとに加える額 2,900円
- 2級地
児童が1人の場合 17,400円
児童が2人の場合 1人分18,000円+4,400円
児童が3人以上1人増えるごとに加える額 2,700円
- 3級地
児童が1人の場合 16,100円
児童が2人の場合 1人分18,000円+4,100円
児童が3人以上1人増えるごとに加える額 2,500円
参考 2021年 生活保護手帳
また、給付額は、経過的措置として世帯人数によって、さらに加算される場合もあるので、具体的な給付額については、お住まいの地域に確認をする必要があります。
母子加算の支給期間
次に母子加算の支給期間について見ていきましょう。
支給期間は以下の通りとなっています。
- 児童が18歳に達する日以後の最初の3月
- 障がい者加算の対象になる児童は20歳になるまで
- 児童を養育する者が再婚するまで(事実婚も含む)
基本的に、父母の一方もしくは両方が欠けているか、これに準ずる状態にあるため、父母の片方または父母以外の者が児童の養育にあたる期間は加算されるということになります。
生活保護を受ける際の注意点とメリット
生活保護を受ける際、注意したい点がいくつかあります。
生活保護を申請すると、親族や元パートナーに福祉事務所から、“申請者を扶養できないか“という連絡がいきます。特に、元パートナーは子供に対して養育費を支払う義務があるため、必ず扶養照会が行われますし、養育費が支払われていない場合は、養育費の請求を行うよう指導されます。ただし、離婚の原因によっては(D Vなど)、連絡がいかないように配慮されます。生活保護相談・申請をするときに、その旨を必ず伝えましょう。
また、生活保護を受給する場合、資産形成ができなくなります。最低限の生活費を超える分で貯金をするということができなくなってしまうので、将来の子供の教育費などであっても、貯金をすることはできません。
さらに、住居や車、娯楽品にも制限がかかるので、不自由を感じる場面も多くなる可能性があります。
生活保護を受給するのであれば、これらの注意点とデメリットを把握しておく必要があります。
生活保護は申請から受給まで時間がかかるうえに審査も厳しいため、まずは使える制度から活用してみるということが無難です。
それでもなお収入が足りないようであれば、生活保護を検討すると良いでしょう。もし、生活保護の要件を満たしている可能性が高いのであれば、お住まいの福祉事務所に相談してみてください。
養育費保証のミライネ
『養育費保証のミライネ』では、養育費を継続的に受け取るためのプランをご用意しております。継続的に養育費を受け取ることは、大切なお子様のためでもあり、そのお子様を育てる親御さんのためでもあります。養育費に関して、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。