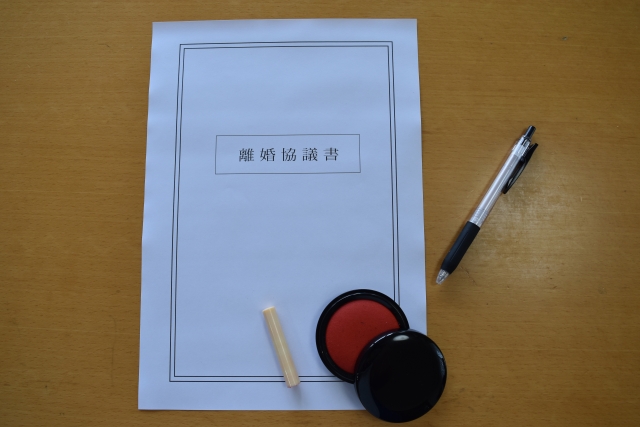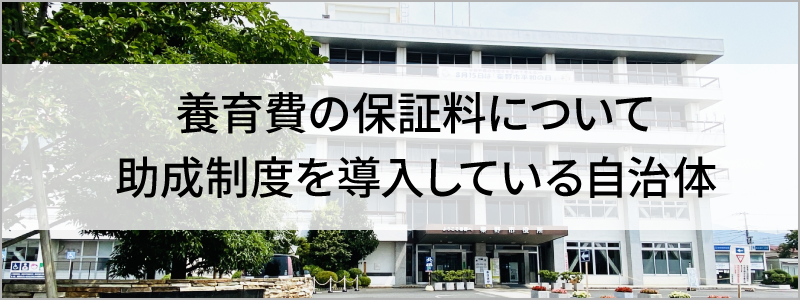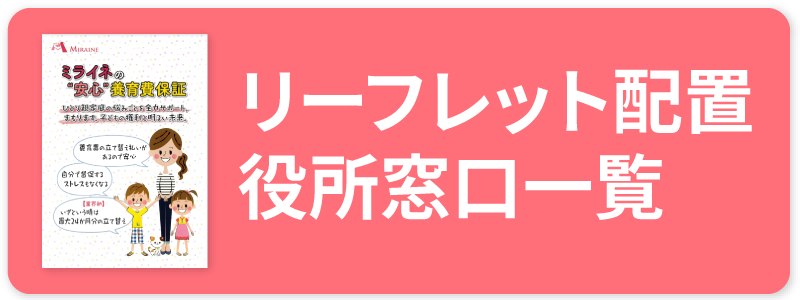再婚時に養子縁組をするべき?養育費はどうなるの?メリット・デメリットを解説
再婚をする際、再婚相手と子供が養子縁組をする場合のメリット・デメリットを解説します。また、元パートナー(実親)から養育費を受け取っている場合は、再婚した場合どうなるかなども合わせて解説します。
養子縁組とは
再婚する際の養子縁組は“普通養子縁組”をする方が多いです。
普通養子縁組は、実の親との法律的な親子関係を継続したまま、再婚相手と新たな親子関係を生じさせるものです。
養子縁組の届出が受理されると、子供は再婚相手の戸籍に入ることになります。戸籍上、子供の記載は「養子/養女」となります。
養子縁組をすると、再婚相手から子供へ相続権や扶養義務が生じます。また、子供の名字は自動的に再婚相手の名字に変わります。
子連れ再婚をして、養子縁組をしない場合は、子供の戸籍や名字は再婚前のままとなります。名字を再婚相手と同じにしたい場合は、家庭裁判所へ『子の氏の変更』を申し立て、許可が下りたら役所に入籍届を出すことになります。
養子縁組をするメリット
前述で解説した“普通養子縁組”をした場合のメリットは以下の通りです。
- 再婚相手も親権を持つ
- 戸籍が同一になる
- 義親(再婚相手)と実親の遺産を相続できる
養子縁組をすると、相続権や扶養義務が発生します。子供(義子)は法律上ほぼ実子と同じ扱いです。養親が亡くなった場合は、実子と同じように養子にも遺産相続の権利が発生します。
養親の父母の遺産相続も可能です。普通養子縁組の場合は実親との関係が続いているので、養子は実親の遺産も相続できます。ただし、特別養子縁組は実親との関係を解消しているので、相続権はありません。
養子縁組をするデメリット
- 再婚・養子縁組を理由に養育費の減額を求められる可能性がある
再婚相手と連れ子が養親縁組をした場合、再婚相手と連れ子の間には親子関係が成立します。そのため、実親・義親の両者の間に扶養義務が発生し、実親・養親が子どもの扶養義務者となります。このような場合、扶養義務は養親が優先になり、実親は2次的な扶養義務者になります。
したがって、養親に扶養能力があれば実親は養育費の減額を請求することが可能になるので、減額請求をされる可能性があります。養育費に関しては次で解説します。
養育費はどうなるの?
再婚をし、再婚相手と子供が養子縁組をした場合でも、実親から養育費を受け取れる権利に変わりはありません。
再婚して養子縁組をした場合、第一次的には、養親となった再婚相手が子供に対して扶養義務を負うことになり、実親の扶養義務は第二次的なものに後退します。前述にもある通り、再婚により家計が経済的に豊かになった場合、養育費の減額を請求される可能性があります。ただし、話し合いや調停などで養育費の額が変更されない限り、公正証書や調停で決めた通りの養育費を支払ってもらうことができます。再婚相手と子供が養子縁組をしたからといって、実親が無断で養育費の支払いを止めた場合、公正証書や調停調書があれば、給与や財産などを差し押さえることも可能です。
養育費でお悩みの方
『養育費保証のミライネ』では、養育費を継続的に受け取るための保証プランを用意しております。また、未払いでお困りの方の集金をサポートするプランも用意しております。
養育費でお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。