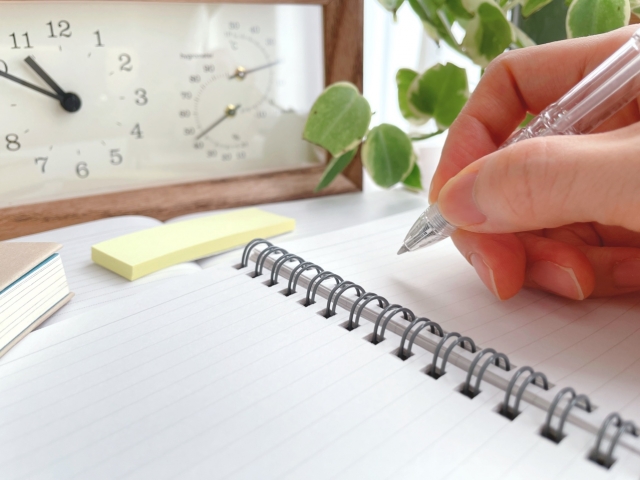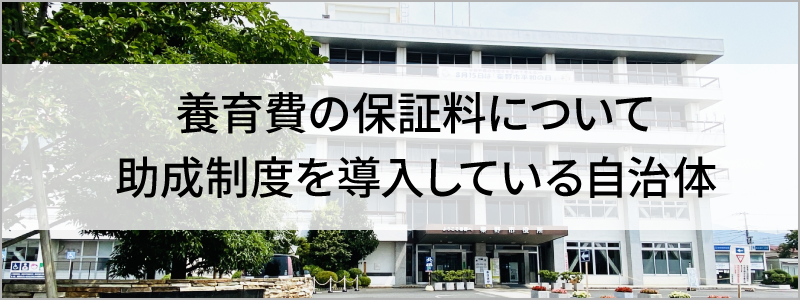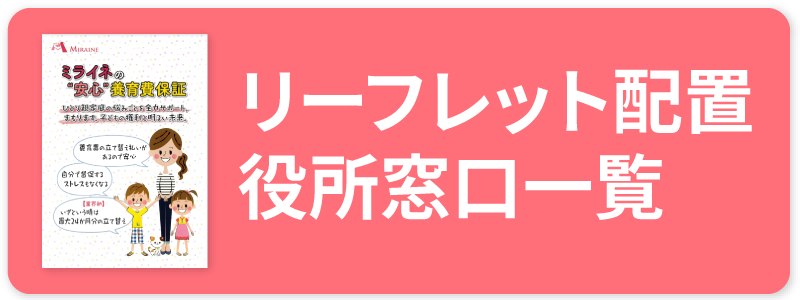もし親権者が亡くなったら?【 親権について 】
ひとり親の方であれば、「もし突然自分が死んでしまったら、残された子供はどうなってしまうの?」と、一度は考えたことがあるでしょう。筆者自身もシングルマザーですので、離婚時だけではなく、ふとした瞬間に不安に思うことが多々あります。
今回はひとり親の方が亡くなってしまった場合、子供の親権はどうなるか、万が一の時のためにどんな準備をしておいた方がいいのかをまとめました。
元パートナーに親権がいく?
自分の死後の親権について、覚えておくべきことが3つあります。
- 元パートナーに自動的に親権が移行することはない
- 親権は子供の主張が尊重される
- 未成年後見人を指定しておくことで、指定した人が親権を取る可能性が高まる
元パートナーに自動的に親権が移行することはありません。ですが、家庭裁判所に親権変更を申し立て、それが認められた場合、親権者になる可能性があります。
元パートナーと離婚後も良好な関係を築いている方ももちろんいらっしゃるでしょう。しかしながら、様々な理由あっての離婚ですから、自分の死後は元パートナーには任せたくないと考えていらっしゃる方も少なくはないでしょう。その場合、「未成年後見人」を指定しておくことで、指定した人が親権を取る可能性が高まります。では、「未成年後見人」とは、どのような制度かを次で解説します。
未成年後見人とは
未成年後見人とは、未成年者に対して親権を行う者がないときなどに、未成年者の法定代理人となる者です。未成年者の法定代理人は、未成年者の利益を保護するために、未成年者にかわって契約などの法律行為を行ったり、財産を管理したりする権限を持っています。
未成年者の法定代理人となるのは、原則として未成年者の親などの親権者ですが、親権者が亡くなった場合は、未成年者の法定代理人が存在しない状態になってしまいます。 そこで、遺言などによって未成年後見人を選任することで、未成年の利益を保護する必要があるのです。 未成年後見人に就任した者は、未成年者の法定代理人として、未成年者のために法律行為や財産管理を行えるようになります。
未成年後見人の選び方は、以下の2つとなります。
- 遺言書を作成し、未成年後見人を指定する
未成年後見人を遺言で選任する場合、家庭裁判所による判断がないので、未成年者や行方不明者などの一定の例外をのぞいて、基本的に誰でも未成年後見人になれます。
また、遺言で選任する場合は、未成年後見人は裁判所の管理下に置かれないので、裁判所に対する財産管理の報告などはありません。 遺言による場合、未成年後見人を自由に選任できる反面、未成年後見人の不正を防止しにくいので、誰を選任するかは慎重に判断しましょう。
- 家庭裁判所に申立てをして選任してもらう
家庭裁判所が未成年者本人や後見人の候補者と面談や、未成年者の親族へ意向照会などが行われます。 裁判所によって未成年後見人が選ばれると、選ばれた未成年後見人に審判書が送付されます。 家庭裁判所に選任された未成年後見人の場合、裁判所の管理の下で、財産管理の報告などを行わなければなりません。
家庭裁判所に申立てをして選任する場合、裁判所がきちんと判断してくる反面、必要な書類を揃えるなど、未成年後見人の事務の負担が大きいのが特徴です。
また、未成年後見人を遺言で指定する場合、自筆証書遺言の場合、様々なリスクがあるので、公正証書遺言をおすすめします。遺言書で指定した場合、役所での手続きも必要になるので、忘れずに行ってください。
次の記事では、親権者の死後のお金に関することを解説します。
養育費保証のミライネ
『養育費保証のミライネ』では、養育費を継続的に受け取るためのサポートをしております。残念ながら、離婚時に公正証書などで養育費の取決めをしていても、継続的な支払いがあるのは約2割と、とても低い水準となっています。養育費の未払いを事前に防ぐことが大切です。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。