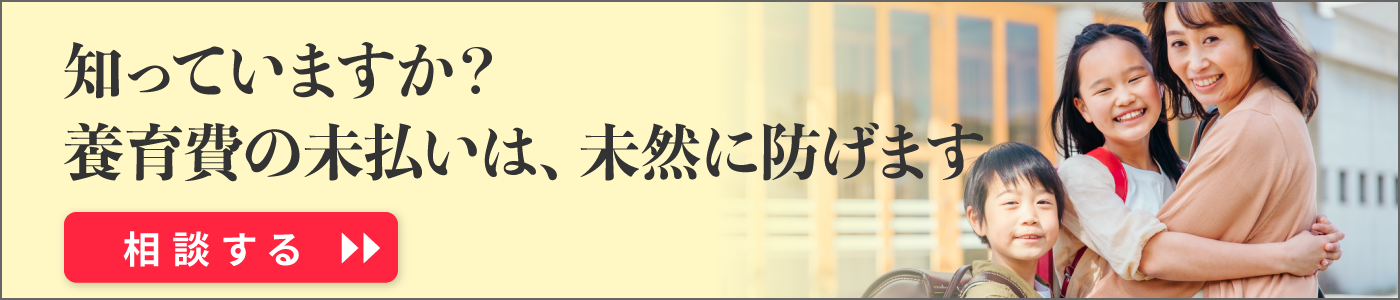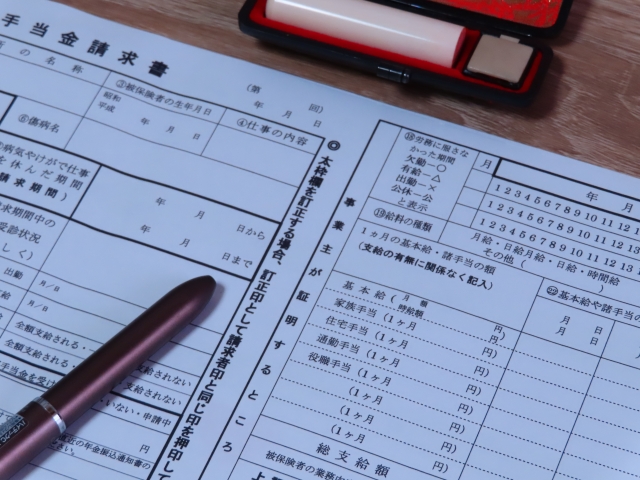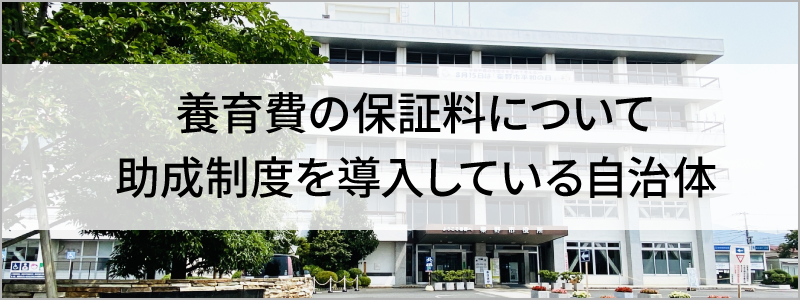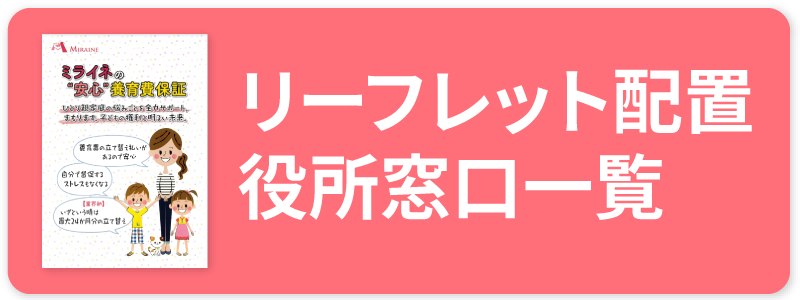財産開示手続きとは?養育費などの不払いを解決しよう
- 公開日
- カテゴリー
- 養育費
2020年4月から法改正によって財産開示手続きが養育費などの不払いに有効な手段になったことをご存知ですか?
そもそも財産開示手続きとは?
債権者の申立てにより、裁判所が債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる手続きの事。
例:支払いを請求しても「お金が無い」と言ってくる場合
→どこにどんな財産を保有しているのか知る為に使える手続き
これによって、差し押さえる財産を発見、特定することができるんです。
財産開示手続きの法改正に伴う変更点
1. 手続の申立てをすることができる者が拡大された
改正前:確定判決・和解調書・調停調書など
⇒ 改正後:金銭支払を定めた公正証書(執行証書→※執行受諾文言付き必須※)、仮執行宣言付判決、確定判決と同一の効力を有する支払督促も追加
2. 財産開示制度に債務者が応じなかった場合(不出頭や虚偽陳述)のペナルティが強化された
改正前:30万円以下の過料(※刑事罰ではない)
⇒ 改正後:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(※刑事罰)
つまり、今までと違うのは、公正証書(執行文)でも対応が可能になった点と、ペナルティが強化されたことにより、罰金だけでなく、刑事罰が課せられる事になるんです。
改正前の、平成29年度の財産開示手続の申立件数のうち、約40%は債務者が不出頭で手続きが終了していました。
改正後の2020年10月20日には、財産開示手続きで裁判所に出頭しなかったことを理由に、書類送検をしたという事例が報道されたこともありました。
強制執行されるよりも、30万円の過料を払った方が安く済むと考えた場合に、出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりする可能性がありましたが、
改正後の今、刑事罰を恐れて、出頭し、真実を陳述することが期待されています。
財産開示手続で債務者が不出頭の場合や、開示された勤務先に対して給与の差押えをしても既に退職していて差押えが失敗した場合に限り、「第三者からの情報取得手続」に進むことができます。
3.「第三者からの情報取得手続」(民事執行法204条~211条)
債務者以外の第三者から、債務者の財産に関する情報を取得することができる制度。債務名義を有する債権者の申立てにより、裁判所が、債務者以外の第三者に対して、情報の提供を命令し、当該第三者が情報を回答することにより、債権者は情報を取得することができる制度の事。
取得できる情報って何があるの?
- 預金口座(銀行、信金、労金、信組、農協など):
有している預貯金口座の支店名、種類、口座番号、額に関する情報の取得。 - 登記所:(法務局《民事執行法205条》)
土地・建物の所有権等に関する情報の取得。(債務者名義の不動産の所在地や家屋番号) - 給与債権(市町村、日本年金機構など):
勤務先の有無、勤務先の氏名・名称・住所といった勤務先の情報の取得。 - 上場株式・国債・投資信託(口座管理機関である証券会社など《民事執行法207条1項2号》
債務者名義の上場株式等の有無、銘柄及び数又は額=上場株式等を差し押さえるために必要な情報
※1. 預金口座に関しては、財産開示手続きを介さなくても、「第三者からの情報取得手続き」から申し立てが可能です。
詳しい流れにつきましてはこちらをご覧ください。
養育費が支払われない場合でも、法改正によって、強制力が高まりました。
諦めるのではなく、ぜひ戦ってみることをお勧めします。
調停証書、執行受諾文言付きの公正証書以外は難しい、でも諦めないで
ただ、調停証書、執行受諾文言付きの公正証書以外でお取り決めをされている方は、残念ながらこの制度を使う事ができません。
だからといって諦めるのではなく、ぜひ養育費保証のミライネにご相談下さい。
養育費保証のミライネでは、養育費未払いでお困りの方に向けたプランもございます。
養育費はお子様の成長の為に受け取る必要な権利です。
お子様の為にも、是非一度お問い合わせください。